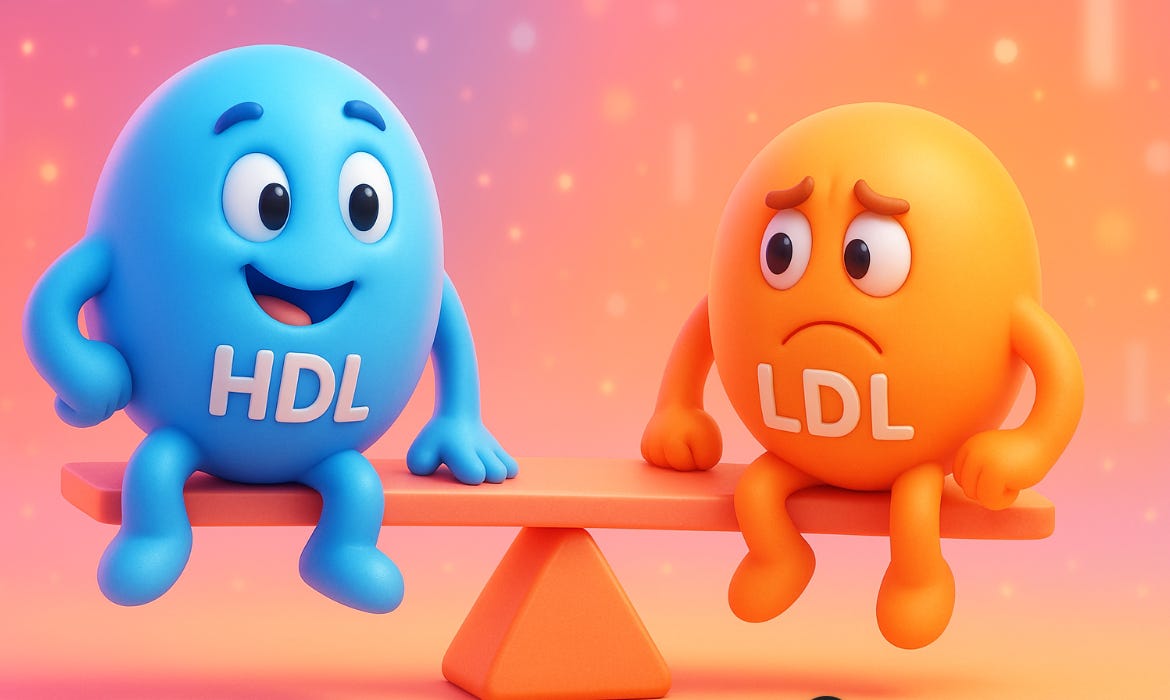血液検査でチェック!②善玉?悪玉?だけじゃない!「コレステロール」はバランスが命! 〜L/H比で見る脂質バランス〜
こんにちは。
前回のメルマガでは、血液検査データから読み解く脂質バランスの第一歩として、「中性脂肪」についてお話ししました。
理想値は「70~90 mg/dL」で、高すぎても低すぎても良くない、という点がポイントでしたね。
今回は、脂質バランスをチェックする上で、中性脂肪と並んで非常に重要な指標となる「コレステロール」について深掘りしていきます!
特に、健康診断の結果でおなじみの「HDLコレステロール」と「LDLコレステロール」に注目し、そのバランスがいかに大切か、そしてそのバランスをどう見れば良いのかを詳しく解説します。
◆ HDLコレステロールとLDLコレステロール、それぞれの役割とは?
「コレステロール」と聞くと、「なるべく摂らない方が良いもの」「健康の敵」といったネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、コレステロールも中性脂肪と同様に、私たちの身体にとって必要不可欠な脂質の一つです。
コレステロールは、
全身の細胞を包む細胞膜の主要な構成成分となる
ホルモン(性ホルモンや、ストレス対応に関わる副腎皮質ホルモンなど)の材料となる
脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の原料となる など、生命維持に欠かせない様々な働きを担っています。
血液検査では、主に以下の2種類のコレステロールが測定されます。
HDLコレステロール(High Density Lipoprotein Cholesterol): 通称「善玉コレステロール」。その主な役割は、血液中や血管の壁にたまった余分なコレステロールを回収し、肝臓へ運び戻すことです。
血管のお掃除役のような働きをするため、「善玉」と呼ばれています。この値が高いほど、動脈硬化のリスクは低いと考えられます。LDLコレステロール(Low Density Lipoprotein Cholesterol): 通称「悪玉コレステロール」。肝臓で作られたコレステロールを、全身の細胞へ運搬する役割を担っています。
細胞が必要とするコレステロールを届ける重要な役割があるのですが、血液中で増えすぎてしまうと、血管の壁に入り込んで蓄積し、プラークと呼ばれる塊を形成します。
これが血管を狭めたり、詰まらせたりする動脈硬化の直接的な原因となるため、「悪玉」と呼ばれています。
このように、「善玉」「悪玉」という呼び名はありますが、どちらも身体に必要な役割を持っています。問題なのは、悪玉と呼ばれるLDLコレステロールが過剰になったり、善玉であるHDLコレステロールが少なくなったりして、両者のバランスが崩れてしまうことなのです。
◆ HDL・LDLコレステロールの理想値は?
では、血液検査の結果で、それぞれの数値はどのくらいを目指せば良いのでしょうか?
HDLコレステロール(善玉): 基準値は一般的に「40 mg/dL以上」とされています。しかし、動脈硬化を予防し、血管の健康を保つためには、より高い方が望ましいと考えられています。
精密栄養学的理想値としては「70~100 mg/dL」の範囲を目指したいところです。
40 mg/dL未満の場合は「低HDLコレステロール血症」と診断され、LDLコレステロール値が正常でも動脈硬化のリスクが高まることが知られています。LDLコレステロール(悪玉): 基準値は「139 mg/dL以下」とされることが多く、140 mg/dL以上は「高LDLコレステロール血症」と診断されます。
しかし、低ければ低いほど良いというわけでもありません。細胞に必要なコレステロールを運ぶ役割があるため、極端に低い(例えば70 mg/dL未満など)と、細胞膜の機能低下やホルモンバランスの乱れなどを招く可能性も指摘されています。
精密栄養学的理想値としては「80~120 mg/dL」あたりを目安にすると良いでしょう。
◆ なぜLDLコレステロールは増えすぎるの? 食生活との関係
LDLコレステロール値が高くなってしまう背景には、遺伝的な要因もありますが、多くの場合、日々の食生活が大きく関わっています。特に、質の悪い脂質の過剰摂取はLDLコレステロールを増加させる大きな原因となります。
具体的には、
飽和脂肪酸の摂りすぎ: 肉の脂身(バラ肉、ひき肉など)、バター、ラード、生クリームといった動物性脂肪に多く含まれます。
また、パーム油(安価なため、加工食品、スナック菓子、インスタント麺、チョコレートなどに広く使われています)も飽和脂肪酸が主体の油です。これらを摂りすぎると、肝臓でのコレステロール合成が促進され、LDLコレステロール値が上昇しやすくなります。トランス脂肪酸の摂取: マーガリン、ショートニング、ファットスプレッドなどに含まれる工業的に作られた脂質です。
これらを原材料に使ったパン、ケーキ、クッキー、ドーナツ、揚げ物などにも含まれます。トランス脂肪酸は、LDLコレステロールを増やし、さらにHDLコレステロールを減らすという、最も避けたい脂質です。
食品表示で「マーガリン」「ショートニング」「加工油脂」などの記載があったら注意が必要です。酸化した油(過酸化脂質)の摂取: 以前お話ししたオメガ6系脂肪酸(リノール酸)を多く含む植物油(サラダ油、大豆油、コーン油など)は、光や熱、空気によって酸化しやすい性質があります。
開封してから時間が経った油、何度も使い回した揚げ油、高温で長時間調理された食品、古いスナック菓子などに含まれる酸化した油(過酸化脂質)は、LDLコレステロールそのものを**より悪玉化(酸化LDL)**させ、血管壁を傷つけやすくし、動脈硬化を強力に推し進めると言われています。
これらの脂質を日常的に多く摂っていないか、ぜひ食生活を振り返ってみてください。
質の良い脂質(オメガ3系脂肪酸など)を選び、質の悪い脂質を避けることが、コレステロールバランスを整える第一歩です。
◆ 最重要チェックポイント!「L/H比」でバランスを見よう!
HDLとLDL、それぞれの数値を確認することも大切ですが、動脈硬化のリスクをより正確に評価するためには、両者のバランスを見ることが極めて重要です。そのための簡単で有効な指標が「L/H比(エルエイチひ)」です。
これは、以下の計算式で簡単に求めることができます。
L/H比 = LDLコレステロール値 ÷ HDLコレステロール値
(例:LDLが120mg/dL、HDLが60mg/dLなら、120 ÷ 60 = 2.0)
この L/H比の**精密栄養学的理想値は「0.9~1.5」**の範囲とされています。
たとえLDLコレステロール値が基準値(139 mg/dL以下)に収まっていても、HDLコレステロール値が低い(例えば40 mg/dL台など)と、L/H比は高くなってしまいます。
一般的に、
L/H比 1.5以下: 理想的な状態
L/H比 2.0以上: 動脈硬化や血栓のリスクが高まり始める(要注意)
L/H比 2.5以上: 心筋梗塞などのリスクがかなり高い(危険水域) と考えられています。
ぜひ、ご自身の血液検査データを使って、このL/H比を計算してみてください。「LDLコレステロール値は大丈夫だったから安心」と思っていた方も、L/H比を計算してみると意外な結果が出るかもしれません。
この数値が0.9〜1.5以下に収まっているかどうか、必ずチェックしましょう!
◆ 中性脂肪とコレステロール、合わせて見ることで理解が深まる!
今週は、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、そしてL/H比について、それぞれの意味と理想値を見てきました。
これらの数値をパズルのピースのように組み合わせて総合的に見ることで、ご自身の脂質の摂取状況や体内の代謝状態を、より深く、立体的に理解することができます。
例えば、
「中性脂肪が高く、HDLが低い」→ 糖質の摂りすぎ?
「LDLが高く、L/H比も高い」→ 飽和脂肪酸やトランス脂肪酸の摂りすぎ?
「中性脂肪は低いが、LDLは高め、L/H比も高い」→ エネルギー不足気味で、かつ質の悪い脂質が多い? 甲状腺機能低下なども隠れているかも?
「全体的に数値が低い(中性脂肪、HDL、LDLすべて低い)」→ 栄養不足、消化吸収能力の低下などが考えられる?
このように、複数の項目を関連付けて見ることで、ご自身の食生活や生活習慣のどこに改善点があるのか、より具体的なヒントが見えてくるはずです。
◆ 次回予告
さて、今回はコレステロールの理想値と、特に重要なバランス指標である「L/H比」についてお伝えしました。基本的な見方は掴んでいただけたでしょうか?
ただ、血液検査の結果は、いつも教科書通りに現れるとは限りません。
「LDLは低いのにL/H比が高い」「中性脂肪とコレステロールの動きが逆」など、少し解釈に迷うような、イレギュラーなパターンを示すこともあります。
そこで来週は、そうした見慣れない検査結果のパターンをいくつかご紹介し、その背景に何が考えられるのかを探るとともに、今回までの脂質に関するお話(オメガ3・オメガ6、中性脂肪、コレステロール)の総まとめをお届けしたいと思います。
ご自身の体からのメッセージをより正確に受け取るために、ぜひ次回もチェックしてくださいね!
今週は以上です。
今週もお読み頂きありがとうございました。
でわ!
【お知らせ①】未来の健康は「知っているか」で変わる!
情報に振り回されず、自分にとって最適な健康法を選びたいと思いませんか?
理学療法・ボディワーク・オステオパシー医学・栄養学など多角的な視点から、プロが「これだけは押さえたい!」健康の基本を5つのテーマで分かりやすく解説。
病気や不調の根本を知り、食事・運動・ストレスと賢く付き合うことで、あなたの健康レベルは確実に向上します。
今こそ、主体的に健康をコントロールする知恵を。
【BASIC】全5講座のテーマ
#1 医療リテラシーの差が健康格差を生む時代へ
#2 病気の黒幕「炎症」を知る
#3 毎日の食事が健康被害を拡大する/改善するー現代栄養学の限界
#4 自主トレーニングに潜む危険性を把握しておこう!
#5 自律神経を知り健康を「コントロール」する。
販売ページはこちら。
※ログインパスワードは「selfcare」です。
【お知らせ②】各種サービスの提供を行なっております。
2025年より、各種有料サービスの提供を開始しました。ご依頼の参考になるようにと、自己紹介のページも作成いたしました。
お仕事のご依頼は「kudochinpt@gmail.com」までご連絡いただければと思います(※「お仕事のご依頼」と件名をつけて頂けると返信が早いと思います)
※今回の記事は、下のボタンからシェアが可能です!この記事がお役に立ちそうな方がいましたら、ぜひシェアして頂ければ幸いです。
本メルマガは月曜と木曜日の定期配信です。メルマガ更新の通知をご希望の方は、下のボタンから登録可能ですので、ご利用下さい。
※本メルマガはあくまで有益な情報提供を目的としたものであり、メルマガ内で紹介している運動やケアの実施、そしてサプリメント等の使用については、主治医または医療専門家の確認・指導の下で行うことを推奨します。
読者が、個人の判断で実践し発生した健康上の不利益については、メルマガの発行者は、一切の責任を負いませんのでご了承ください。