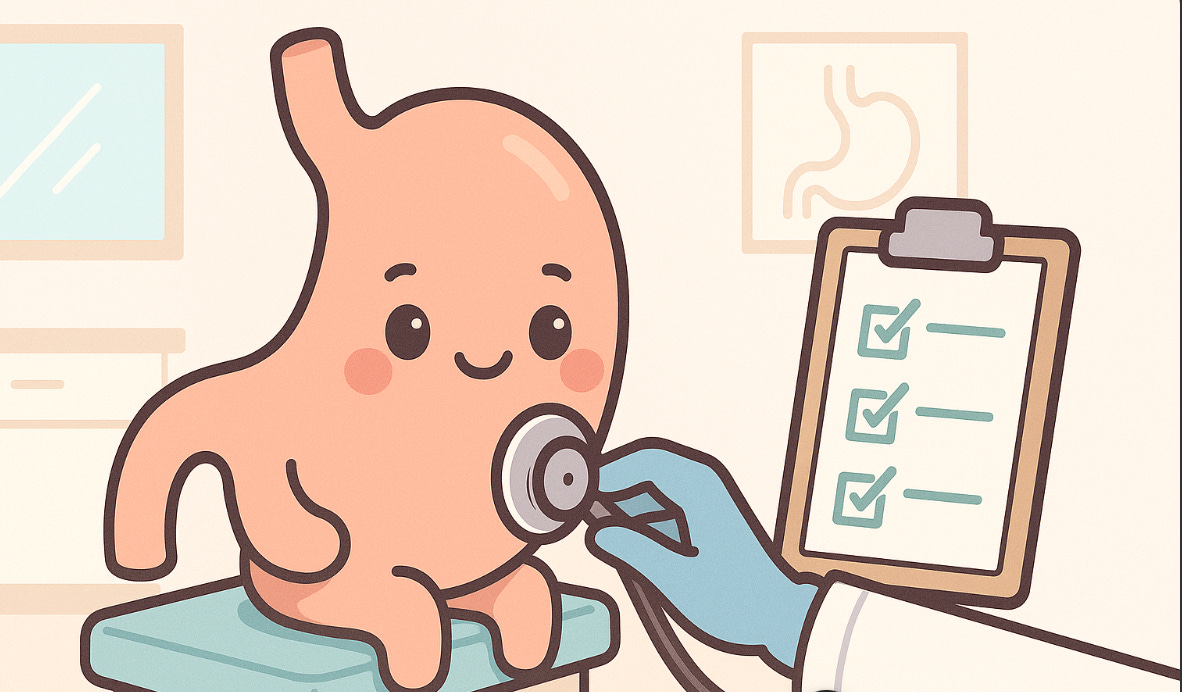あなたの体は満たされてる?「たんぱく質」摂取状況セルフチェック! ①タンパク質の摂取状況のチェック方法とは?
こんにちは!
前回のシリーズでは、「脂質」について、その重要性から選び方、そして血液検査データの読み解き方までを詳しく見てきましたね。
私たちの体にとって、どの栄養素もバランスが大切であることを再認識いただけたのではないでしょうか。
さて、今回から数回にわたってスポットライトを当てるのは、私たちの身体の「主役」とも言える栄養素、「たんぱく質」です!
筋肉や骨、皮膚、髪の毛、爪はもちろんのこと、体の機能を調整するホルモンや酵素、免疫システムを担う抗体など、私たちの体はまさにタンパク質でできていると言っても過言ではありません。
美と健康の土台を築き、生命活動を維持するために、一時も欠かすことのできない存在なのです。
「たんぱく質が大切なのは、もう十分わかっているわ!」という方も多いと思います。
では、質問です。あなたは毎日、本当に十分な量のたんぱく質を摂れているでしょうか? そして、もっと大切なのは、摂ったたんぱく質を、きちんと体の中で消化・吸収し、活用できているでしょうか?
今回はまず、「①タンパク質の摂取状況のチェック方法とは?」と題して、もしかしたらあなたの体が発しているかもしれない「たんぱく質不足」のサインや、たんぱく質を効率よく利用するための最初の関門である「消化・吸収力」、特に「胃酸」の状態を見極めるヒントについて、詳しくお話ししていきます。
◆ それ、もしかして「たんぱく質不足」のサインかも? 多方面に現れる影響とは
たんぱく質が不足すると、私たちの体には実に様々な、そして意外な影響が現れてきます。
「最近なんだか調子が悪いな…」と感じているその不調、もしかしたらタンパク質不足が関係しているかもしれません。
では、以下のようなサインが現れていないかチェックしてみてください。
筋肉量の低下・筋力ダウン、疲れやすさ: 最もイメージしやすい影響ですね。筋肉量が減ると基礎代謝も低下し、太りやすく痩せにくい体質になったり、疲れやすさを感じたり、姿勢が悪くなったりします。
肌・髪・爪のトラブル: 美しい肌のハリや弾力を保つコラーゲンも、実はたんぱく質の一種です。不足すると、肌の乾燥、シワ、たるみが目立つように。
また、髪の毛の主成分もケラチンというたんぱく質なので、パサつき、枝毛、抜け毛の増加、コシのなさといった悩みや、爪が割れやすい、薄い、二枚爪になるといったトラブルも現れやすくなります。免疫力の低下: 免疫細胞や抗体など、私たちの身体を外部の敵から守る免疫システムも、たんぱく質を主原料としています。
そのため、不足すると風邪を引きやすくなったり、一度引くと治りにくくなったり、感染症にかかりやすくなったりします。集中力・思考力の低下、精神的な不安定さ: 脳内の神経伝達物質(セロトニン、ドーパミン、GABAなど)もアミノ酸(たんぱく質の構成要素)から作られます。
これらが不足すると、やる気が出ない、集中力が続かない、頭がボーッとする、イライラしやすい、気分が落ち込みやすいといったメンタル面の不調にもつながります。むくみやすくなる: 血液中のたんぱく質(特にアルブミン)は、血管内の水分量を適切に保つ役割があります。アルブミンが不足すると、血管から水分が漏れ出しやすくなり、むくみの原因となることがあります。
貧血(特に鉄欠乏性貧血の背景に): 血液中で酸素を運ぶヘモグロビンは、鉄とたんぱく質(グロビン部分)からできています。
鉄分を摂っていても貧血が改善しにくい場合、たんぱく質不足が隠れていることもあります。
これらのサイン、心当たりはありませんか? 複数当てはまるようであれば、たんぱく質の摂取状況や利用効率を見直す必要があるかもしれません。
◆ たんぱく質活用の鍵!「胃酸」はしっかり出ていますか?
「たんぱく質が足りないなら、明日からプロテインを飲もう!お肉や魚をもっと食べなきゃ!」 そう意気込む前に、ぜひ一度立ち止まって考えていただきたいことがあります。
それは、「あなたの身体は、摂ったたんぱく質をきちんと消化・吸収できる準備ができているか?」ということです。
たんぱく質は、そのままでは分子が大きすぎて体に吸収できません。口から入ったたんぱく質は、まず胃で「胃酸」と「ペプシン」という消化酵素によって大まかに分解され、その後、十二指腸や小腸でさらに細かくアミノ酸やペプチドに分解されて、ようやく吸収されます。
この最初のステップである胃での分解が非常に重要です。
そして、ここで鍵となるのが「胃酸」の働きです。
胃酸(主に塩酸)には、
食べ物と一緒に入ってきた細菌やウイルスを殺菌する
たんぱく質をある程度変性させ、消化酵素が働きやすくする
たんぱく質分解酵素である「ペプシン」を活性化させる(ペプシノーゲンという不活性な状態から、働くペプシンへ変える) といった重要な役割があります。
つまり、胃酸が十分に分泌されていなければ、ペプシンは活性化されず、たんぱく質の本格的な分解がスタートできません。
その結果、未消化のたんぱく質が腸へ送られ、腸内環境を悪化させる原因(悪玉菌のエサになるなど)になったり、せっかく摂った栄養が十分に吸収されなかったりするのです。
いくら良質なたんぱく質をたくさん摂っても、最初の消化ステップでつまずいていては、非常にもったいないですよね。
◆ あなたの「胃酸力」は大丈夫? 簡単セルフチェック法
では、ご自身の胃酸がきちんと、そして十分に出ているかどうか、どうすれば推測できるのでしょうか?
いくつかご家庭でできる簡単なセルフチェックのヒントをご紹介します。
食後の「胃のサイン」を観察する
食後、特に肉や魚などのたんぱく質を多く含むものを食べた後に、胃が重たい、いつまでももたれる感じがする。
ゲップがよく出る、お腹が張りやすい(特に上腹部)。
あまり量を食べていないのに、消化に時間がかかり、次の食事の時間になってもお腹が空かない。 これらの症状が頻繁に見られる方は、胃酸の分泌が少ない、あるいは胃の働き自体が低下している可能性があります。
胃酸の分泌は、加齢、ストレス、睡眠不足、食生活の乱れ、ピロリ菌感染(または既往)など、様々な要因によって低下することが知られています。
「ビーツ尿テスト」にトライ!
これは、鮮やかな赤紫色が特徴の野菜「ビーツ」を使った、胃酸の分泌状態を推測する手軽なテストです。(※医学的な診断法ではなく、あくまで家庭でできる目安の一つとして捉えてください。) ビーツに含まれる「ベタシアニン」という赤い色素は、通常、強い酸性である胃酸によって分解・無色化されます。しかし、胃酸の分泌が少ないと、この色素が十分に分解されずに腸から吸収され、尿として排出される際に赤~ピンク色を帯びることがあります。やり方:生のビーツ(または100%ビーツジュース)を100g~200g程度(ジュースならコップ1杯程度)摂取します。その後、数時間~半日以内(特に次の排尿時)の尿の色を観察します。
判定の目安:尿の色が明らかに赤~ピンク色になった場合は、胃酸が少ない(低胃酸)のサインかもしれません。尿の色がほとんど変わらない(無色~通常の黄色)であれば、胃酸は比較的しっかりと分泌されていると考えられます。
注意点:このテストはあくまで簡易的な目安です。ビーツの摂取量やその時の体調、他に摂取している食品やサプリメント(例えばビタミンB群は尿を濃い黄色にします)によっても結果は変動します。一度の結果で判断せず、何度か試してみるのも良いかもしれません。
血液検査データから推測するヒント お手元に健康診断などの血液検査の結果があれば、以下の項目もタンパク質の利用状況や胃酸の状態を推測する手がかりになることがあります。
AST (GOT) や ALT (GPT) が低すぎる場合: ASTやALTは主に肝機能の指標として知られていますが、これらはアミノ酸の代謝(作り替え)に不可欠な酵素であり、その働きには補酵素としてビタミンB6が必要です。体内のたんぱく質やビタミンB6が慢性的に不足していると、これらの酵素の活性が低下し、検査値が基準値よりもかなり低く(例えば一桁など)なることがあります。
BUN (尿素窒素) が基準値よりも低い場合: BUNは、たんぱく質が体内で利用された後に生じる老廃物(尿素)に含まれる窒素の量を示しています。
たんぱく質の摂取量が極端に少ない場合や、肝臓での尿素回路(アンモニアを尿素に変換する経路)の働きが低下している場合に、BUNの数値が基準値を下回ることがあります。
これらの項目が基準値下限よりも明らかに低い状態が続く場合は、たんぱく質の摂取不足、あるいは消化吸収不良による利用効率の低下が背景にある可能性が疑われます。
◆ まとめ:「プロテイン摂取!」の前に、まず「受け入れ態勢」の確認を!
いかがでしたでしょうか? 「最近、肌も髪も調子が悪いし、疲れやすいのは、やっぱりたんぱく質不足だったのかも…」と感じた方もいらっしゃるかもしれませんね。
しかし、そこで短絡的に「よし、明日からプロテインパウダーをたくさん飲もう!」「無理してでもお肉をたくさん食べよう!」と考えるのは、少し早いかもしれません。
その前に、まず大切なのは、ご自身の体が、摂ったたんぱく質をきちんと**「分解」し「吸収」できる「受け入れ態勢」**にあるかどうかを確認することです。
特に、たんぱく質消化の最初の関門である「胃酸」がしっかり分泌されているかは、非常に重要なチェックポイントです。
もし、今回ご紹介したセルフチェックで「胃酸不足かも…」というサインが見られた方は、まずは胃腸の調子を整え、胃酸の分泌をサポートするような生活習慣や食事を心がけることから始めてみましょう。(その具体的な方法については、次回の記事で触れますね!)
身体がたんぱく質を受け入れる準備が整ってこそ、摂取した栄養が真に活かされます。
では、身体がたんぱく質を効率よく利用できる状態にある、あるいはその準備を整えつつあるとして、次に知りたいのは「じゃあ、実際にどのように、何を、どれくらい摂ればいいの?」ということですよね。
次回は、いよいよ「②美と健康の土台を作る、正しい摂り方とは?」と題して、あなたに本当に必要なたんぱく質の量、どんな食品から摂るのがベストなのか、そして消化吸収をさらに高めるための具体的な食事の工夫や摂取タイミングについて、詳しくお伝えしていきます!
どうぞお楽しみに!
【お知らせ】
2025年6月よりメルマガがリニューアル!「女性のための慢性腰痛セルフケア通信」というニュースレターを開始します!
詳細はこちらのメルマガ記事でご紹介しています。
ぜひ配信開始をお楽しみください!